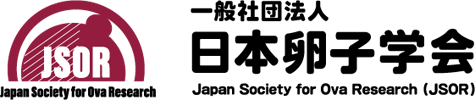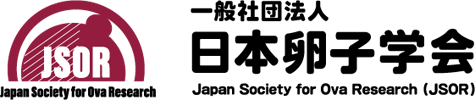
資格に関してのQ&A
胚培養士全般
- 認定資格名の英語表記を教えてください。
- 生殖補助医療胚培養士 :Embryologist for human assisted reproductive technology
生殖補助医療管理胚培養士:Senior embryologist for human assisted reproductive technology
- 学会を退会しても胚培養士としての資格は継続されますか。
- 認定基本規定の
第6章 生殖補助医療胚培養士資格の喪失 第19条記載の通り、
会員資格の喪失とともに認定資格も喪失となります。
胚培養士認定(新規)
- 生殖補助医療臨床実務経験証明書についての質問です。申請書類の提出時では実務が1年未満ですが、試験日には1年以上となります。実務経験証明書の記載は申請時点までの期間を書くのでしょうか、試験日を書くのでしょうか。
- 審査日までに1年を満たしていれば受験できます。実務経験証明書は申請時点までの期間を記載してください。
- 資格審査申請での「30症例の実施記録」について胚移植をせず、全胚凍結になった症例も記入してよいでしょうか。
- 全胚凍結になった症例も含めて大丈夫です。臨床妊娠の箇所は「全胚凍結を実施。その後の融解胚移植で妊娠」などと記載してください。書式のスペースがない場合には、2枚にまとめてください。
- 胚培養士資格認定審査で、ART 生涯研修コースは学会に1回参加したものとして扱われますか。
- 日本受精着床学会が開催する「ART 生涯研修コース」は、資格更新の場合のみ1回カウントとなります。新たに申請する場合は学会参加数に数えることができません。関連学会は一般社団法人日本卵子学会 生殖補助医療胚培養士資格認定審査規則第4章 第12条をご参照ください。
- 資格認定審査に年間症例が30例以上必要との事でしたが、どこに記載されているのでしょうか。
- 30症例につきましては内規ではなく、毎年秋に公表する申請要項に記載されています。ホームページのインフォメーション内に前回の要項が掲載されておりますので参照してください。なお、体外受精・胚移植法実施記録(30症例)は、年間でなく実務期間中の合計数となります。症例報告がきちんと書かれていない場合は不合格となることがございます。また全胚凍結になった症例も含めて大丈夫です。臨床妊娠の箇所は「全胚凍結を実施。その後の融解胚移植で妊娠」などと記載してください。書式のスペースがない場合には、2枚にまとめてください。
- 認定審査の内規に「学会及び関連する学会に、最近1年以内に2回以上参加していること」とありますが、最近の1年間とはいつを指しますか。
- 審査がある年度の前の年度(4月から3月まで)を指します。
なお、更新の場合「最近5年間」とは、審査がある年度の前の年度(4月から3月まで)までの直近の5年間を指します。
上記より、更新年度に開催の日本卵子学会は、5年後の更新時に必要な 学会参加数にカウントしています。
胚培養士認定(更新)
- 認定審査の発表があった日本卵子学会への学会参加は学会参加に加えてよいでしょうか。
- 認定年度に開催の日本卵子学会は、5年後の更新時に必要な学会参加数にカウントしています。倫理講習会は、認定期間中に受講する必要があるため資格をお持ちでない方には発行されません。
- 育児休暇等で休職していた期間の学会参加は資格更新時に書類審査で認められますか。
- 休職期間中の学会参加もカウントされます。認定期間中に休職された場合は、凍結手続きが必要となります。
- 更新予定者だったのですが、更新することを忘れてしまいました。どうしたらよいでしょうか。
- 更新申請期間までに凍結を含め手続きをされなかった方につきましては、資格制度規約規程第6章第19条資格の喪失に関する項目の(3)「生殖補助医療管理胚培養士及び胚培養士の資格が更新されなかった場合」に該当となり、資格を喪失します。資格取得には再受験となります。
胚培養士認定(更新)凍結
- 資格の凍結を届けたいのですがどのようにすればよいでしょうか。
- 毎年秋に、各種申請要項がホームページに掲載されます。ご自分の資格更新年度の申請時期に更新要項の中の凍結希望届のみをご提出下さい。
- 資格凍結期間は会費を納めなくてよいのでしょうか。
- 資格認定者は資格凍結を認めていることから資格凍結中も年会費のご納入をお願いしております。 なお、2年以上会費未納の場合、会員資格が喪失となり認定資格も喪失となります。
- 資格の凍結期間を解くには申請が必要でしょうか。
- 申請の必要はありません。届出いただいた資格凍結期間に応じて、ご自分で更新年度を忘れないようにしてください。資格喪失とならないよう、十分ご注意願います。
- 資格認定者ですが、休職のため資格の凍結を行いたいと思っていましたが、申請の期間を過ぎてしまいました。どのようにしたらよいか教えてください。
- 資格の更新審査や凍結の申請書類受付期間は厳守していただいております。期間内に申請または凍結希望届のご提出が無い場合は、誠に残念ですが、資格喪失となり再度取得には改めて受験していただくこととなります。
- 凍結した場合、更新に必要な学会参加は、休職前後の5年で満たす必要があるというこでしょうか?
- 本来の更新における対象期間に加えて、凍結期間の参加も
カウントできます。
管理胚培養士(更新)
- 管理胚培養士と胚培養士の認定を持っていますが、今年が胚培養士の資格更新の時期になっています。管理胚培養士の資格だけを更新していればいいのか、胚培養士の資格も更新する必要があるか教えて下さい。
- 管理胚培養士認定後は、胚培養士ではなく管理胚培養士として登録となります。従いまして、今後は管理胚培養士としての更新のみとなります。